読書は人生を豊かにするもの。
しかし、間違った考えを持っていると、その効果を最大限に活かせません。
特に誤解されがちなのが「速読」「多読」「選書」の3つです。この記事では、それぞれの誤解と正しい読書法について解説します。
速読は本当に有効なのか?

「速く読めるようになれば、たくさんの知識が身につく!」と思っていませんか?
実は、アメリカのカリフォルニア大学の研究によると、速読をすると理解度が大幅に低下することが判明しています。
読むスピードを上げることで、内容をきちんと理解できないまま読み進めてしまうのです。
私自身、速読を試したことがあります。
最初は「おお、こんなに早く読めるようになった!」と興奮しましたが、数日後に内容を思い出そうとしてもほとんど覚えていませんでした。
また、以前ニュースで「速読選手権のチャンピオンが『ハリー・ポッターと賢者の石』を47分で読んだ」という話を聞きました。
彼の感想はこうでした。
「これはページをめくる手が本当に止まらない素晴らしい一冊だ。最高に楽しかった。子どもたちには大人気ですし、子どもが好きそうなシーンもたくさんあります。でも、ちょっと悲しいシーンもありますね。」
どうでしょう?
キャラクターの名前やストーリーの山場に一切触れていません。
つまり、ほとんど内容を理解していないのです。
「読むスピードを上げると理解度は下がる」
これは読書の基本ルールとして覚えておきましょう。
多読=知識が増える、は間違い
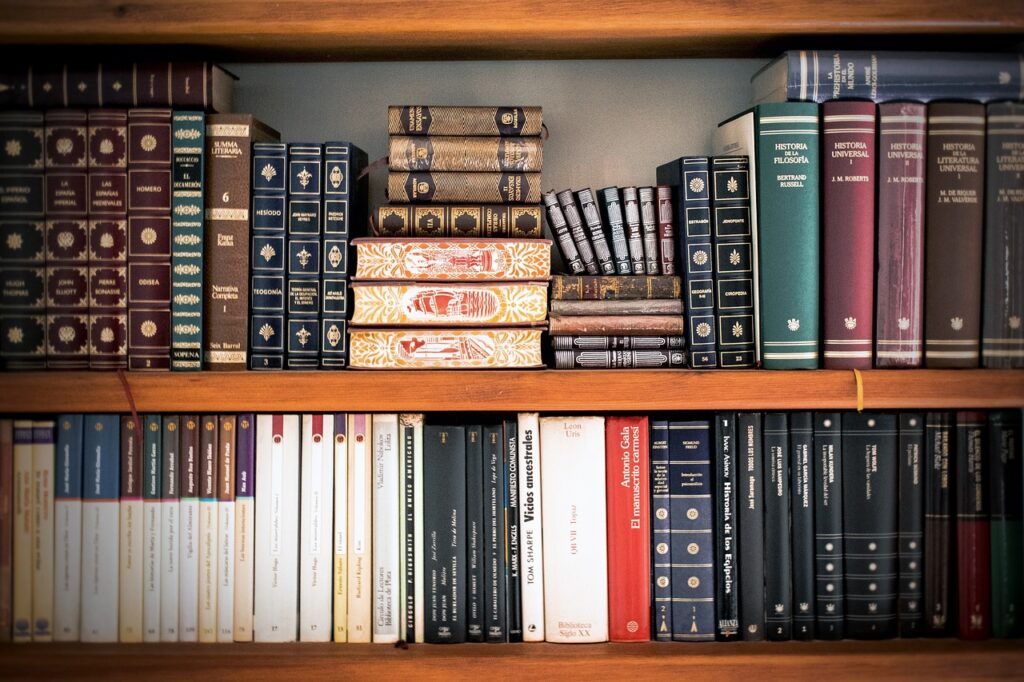
「たくさん本を読めば、それだけ知識が増える」と思っていませんか?
確かに、多くの本を読むことで視野は広がります。
しかし、むやみに多読をしても、結局は情報が頭の中を通り過ぎるだけになってしまいます。
私もかつて「年間100冊読むぞ!」と意気込んで読書に励みました。
しかし、振り返ってみると、印象に残っている本はほんの数冊だけでした。
本当に知識を定着させたいなら、量よりも質を重視し、読む前に「目的」を明確にすることが重要です。
何のためにこの本を読むのかを考えることで、読書の効果は劇的に向上します。
選書は「役立つ本を選ぶ」ことではない
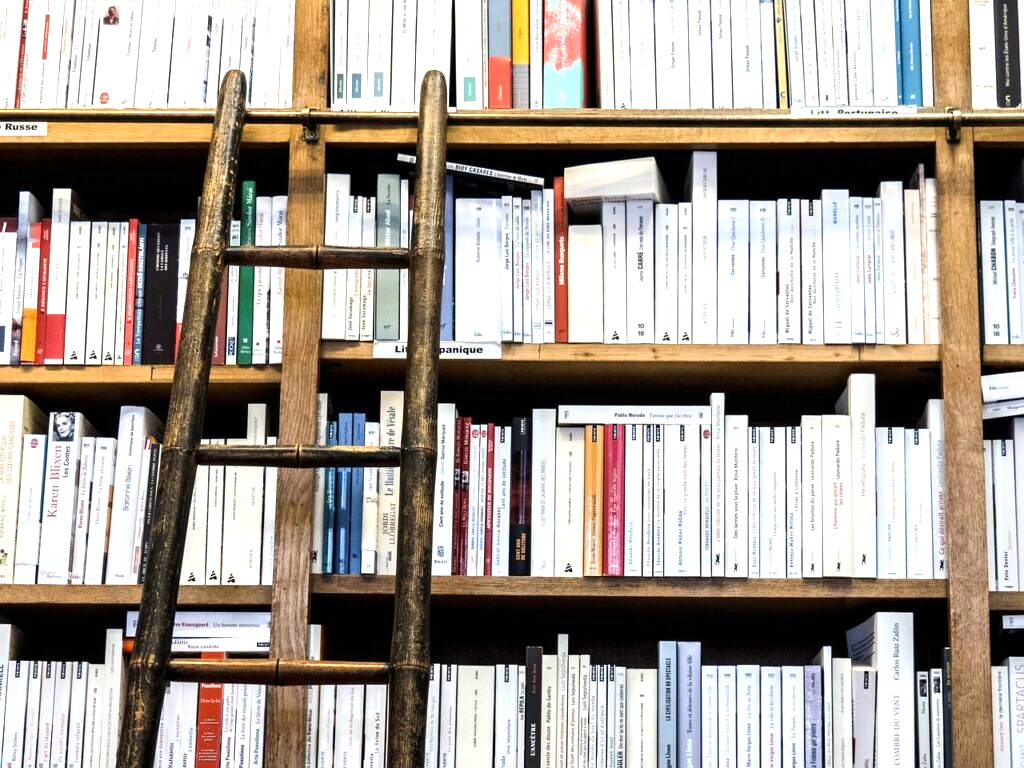
「どうせ読むなら、役に立つ本を選びたい」と思うのは当然です。
しかし、「役に立つ本」とは、一概に決められるものではありません。
たとえば、ある人にとっては最高のビジネス書でも、別の人にとってはまったく響かないこともあります。
大切なのは、「自分にとって役立つ知識や情報を得られる本かどうか」です。
私自身、過去に「ベストセラーだから」と飛びついた本が、まったく身にならなかったことが何度もあります。
逆に、たまたま手に取った一冊が人生を変えるような知識を与えてくれたこともありました。
つまり、本を選ぶときは、「この本は良い本か?」ではなく、
「今の自分が求めている知識は何か?」を考えることが重要なのです。
まとめ
読書をより効果的にするために、次の3つを意識しましょう。
- 速読は理解度を下げる → ゆっくり読んで、しっかり理解する。
- 多読よりも「目的を持った読書」 → 読む前に何を学びたいのかを明確にする。
- 選書は「良い本」を探すのではなく、「自分に必要な本」を探す → 今の自分にとって役立つ本を選ぶ。
読書は「量より質」。
しっかりと理解し、自分の知識として活かせる読書を心がけていきましょう!
別記事でも「読書の質を上げる方法」を解説していますので、あわせてご覧ください!
↓
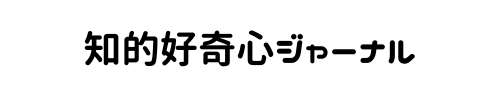
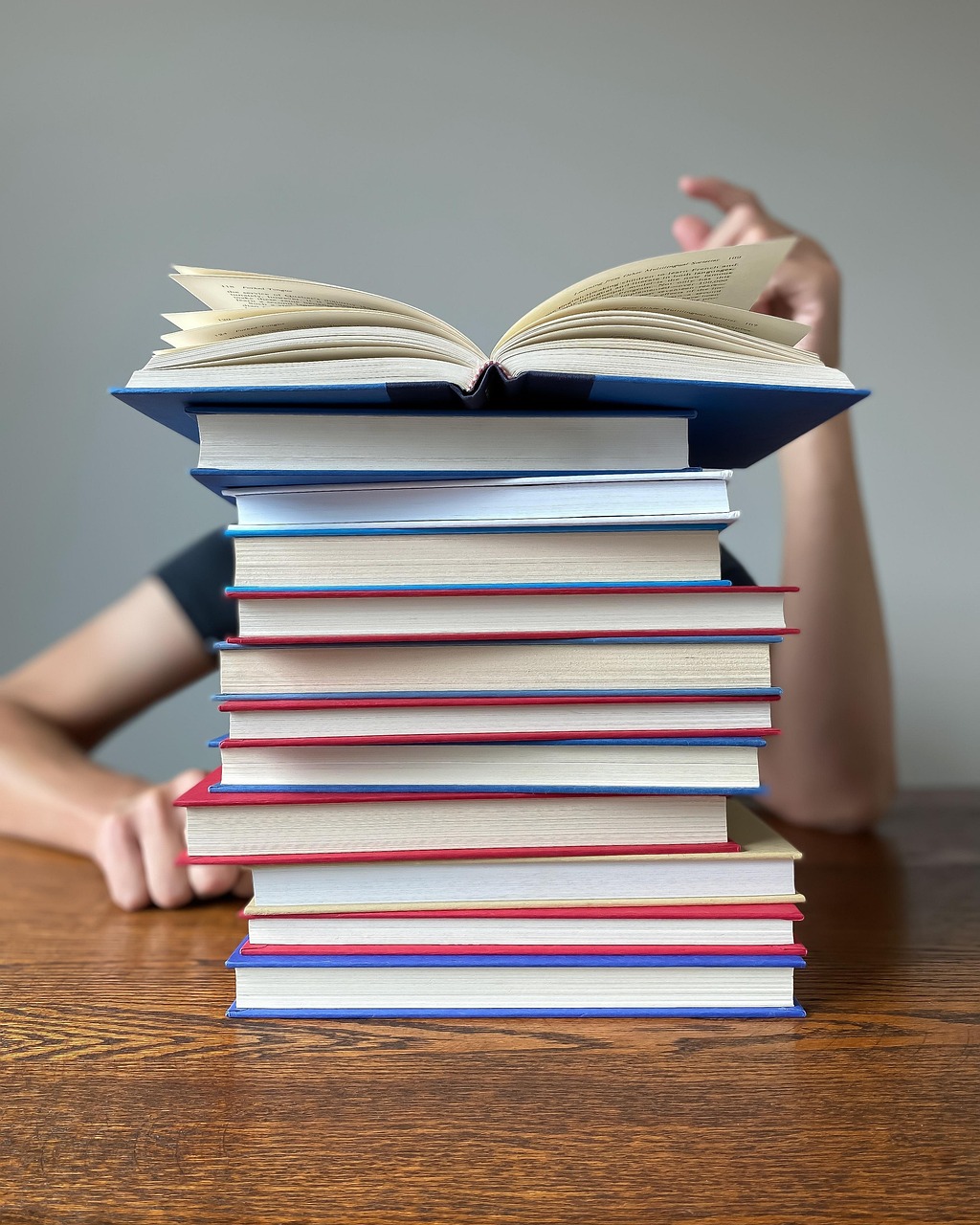



コメント