「正解がない時代」と言われる現代。
そんな時代を生き抜くために必要なのが「アート思考」です。
私自身、長年ブログを書き続ける中で、何度も「どうすれば読者に価値を届けられるか?」と試行錯誤してきました。
その過程で気づいたのが、「正解を探すのではなく、自分なりの答えを生み出すこと」が大切だということ。
まさにアート思考の考え方です。
この記事では、アート思考とは何か、そしてその鍛え方について解説します。
そもそもアート思考とは?

アート思考とは、「自分だけの視点で物事を見て、自分なりの答えを生み出す思考法」のことです。
例えば、絵画や彫刻を制作するアーティストは、決められた「正解」を目指すのではなく、試行錯誤しながら「自分なりの表現」を生み出します。
この思考法が重要視される理由は、現代社会が「唯一の正解がない問題」にあふれているからです。
AIやテクノロジーの発展により、単純な「正解探し」なら機械のほうが優秀な時代。
そんな中で生き残るためには、自分なりの視点を持ち、新しい価値を生み出せる力が求められています。
アート思考の重要な3要素は以下の通りです。
- 表現:自分なりの答えを生み出すこと
- 興味:好奇心を持ち、疑問を持つこと
- 探求:興味を深掘りし、答えを見つけるプロセス
つまり、「自分の興味を持ち、それを探求しながら、自分なりの表現を生み出す」ことこそがアート思考なのです。
なぜ学校教育ではアート思考が育ちにくいのか?

私がこの考え方に共感したのは、「なぜ日本の学校ではアート思考が育ちにくいのか?」という疑問を持ったことがきっかけです。
例えば、美術の授業では「絵を上手に描くこと」や「過去の作品を覚えること」が重視されがち。
しかし、本来の美術の役割は「自分の視点を持つこと」ではないでしょうか?
学校教育は、「正解を探す力」を鍛えることには長けていますが、「自分なりの答えを作る力」を養う場面は少ないのです。
そのため、成長するにつれて「決められた答えに従う」ことが習慣化し、自分なりの視点を持つことが難しくなります。
しかし、大人になってからでもアート思考を鍛えることは可能です。
ここからは、実践的なアート思考の鍛え方を紹介します。
アート思考を鍛える2つの方法

① アウトプット鑑賞
美術館で絵を見るとき、ただ眺めるだけではなく、「アウトプット」しながら鑑賞すると、自分なりの視点が磨かれます。
やり方
- 1枚の絵をじっくり見る
- 気づいたことを声に出したり、紙に書き出したりする
- 他の人と感想をシェアする
例えば、ゴッホの「ひまわり」を見たときに「鮮やかな黄色が印象的」と感じたとします。
そこから「なぜそう感じるのか?」を深掘りすると、「背景とのコントラストが強いから」など、新たな発見につながります。
この習慣を持つと、普段の生活でも「自分なりの視点」を持ちやすくなります。
② 「意見」と「事実」を意識する
アート思考を鍛えるには、「意見」と「事実」を意識してアウトプットすることが重要です。
やり方
- 意見が出たら、事実を探す(例:「この絵は明るい雰囲気」→「なぜ?」→「黄色が多く使われているから」)
- 事実が出たら、意見を考える(例:「この絵には曲線が多い」→「それによって、やわらかい印象を受ける」)
この方法を繰り返すことで、自分の視点を言語化し、独自の考えを持つ練習になります。
アート思考の原点は「自分の好きなこと」
アート思考を身につけるために最も大切なのは、「自分の好きなことを知る」ことです。
私自身、ブログを書いていると「なぜこのテーマが気になるのか?」と深掘りする機会が多くあります。
結局のところ、「好きなこと」は自分なりの視点を持つ原点になり、アート思考の基盤を作ってくれるのです。
社会の変化が激しい今、「正解を探す力」だけでは生き残れません。
「自分なりの答えを作る力」を育てるために、ぜひアート思考を実践してみてください!
別の記事では「頭のいい人の思考」について紹介しています。こちらもチェックしてみてください!
↓
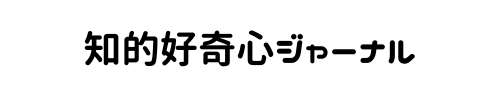




コメント